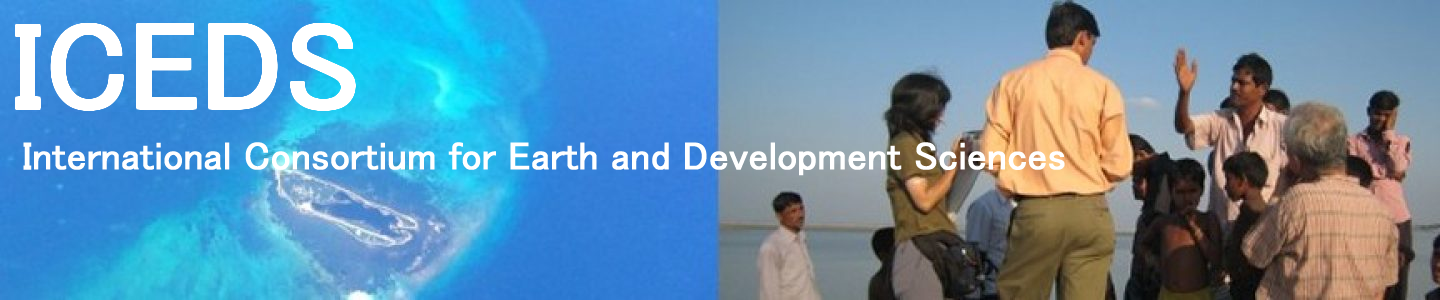Archives for Seminar
Workshop on Disasters due to Premonsoon Severe Local Storms (SLSs) over the Northeastern Indian Subcontinent (NEIS) / 23 May
Premonsoon rainfall in Northeastern (NE) Indian subcontinent (NEIS) is now emerging as new hotspot of Asian monsoon research of climate change impact. Devastating tornadoes, floods and lightning activities due to…
Workshop on “Coordinated Observations and Modelling Strategies for Pre-monsoon Severe Storms in Northeast India” / 5 Mar.
Severe premonsoon storms, including Nor'westers and associated convective systems, significantly impactNortheast India, causing damage to infrastructure, agriculture, and human life. The need for a coordinated observational and modeling approach is…
HAELE-14 “Society and Smells – the Dynamics of Cultural Change” / 2 Feb.
A part of the international joint workshop between a team research of the International Institute forJapanese Studies: ’Mouths and Noses: A Cultural History of the Junctures between the Human Bodyand…
GCS55 Regionality debates beyond the hard and soft clustering dichotomy / 19 Sep.
Date:September 19, 2024, 13:00-15:00 JST (Zoom online hybrid flexible)Place:ICEDS Room (Enkaku Kyoiku Chousa Kenkyu-shitsu),Saiwai-machi Campus, North, Kagawa University, Building 2, 2nd Floor. Program: 13:00-13:05Opening remarks 13:05-13:30: Presentation 1Nazmul Huda (Bangladesh…
GCS53 Wages and Prices in Recent Decades Bangladesh / 2 Aug.
Date:August 2, 2024, 10:00-12:00 (Zoom online hybrid flexible)Place:ICEDS Room (Enkaku Kyoiku Chousa Kenkyu-shitsu),Saiwai-machi Campus, North, Kagawa University, Building 2, 2nd Floor. Program: 10:00-10:05Opening remarks 10:05-10:40: Presentation 1Nazmul Huda (Bangladesh University…
GCS50 An Environmental History of the Colonial Period / 12 July.
Date:12 July 2024, 14:00-16:00 (JST) (Zoom online hybrid flexible) Place:ICEDS Room (Enkaku Kyoiku Chousa Kenkyu-shitsu), Saiwai-machi Campus, North, Kagawa University, Building 2, 2nd Floor. July 12, 14:00-16:00: Lecture Dr Robert…
HAELE-10 on February 2nd
We are thinking of producing an Asian edition of Altered Earth: Getting the Anthropocene Right, edited by Julia Adeney Thomas, tentatively titled Altered Earth in ; HAELE will build on the past…
[2/20開催]GCS46 ゴミ焼却灰とバイオマス発電焼却灰の再資源化とカーボンニュートラルへの貢献
セミナー 講演:吉田秀典(香川大学創造工学部教授) 趣旨と概要 近年,カーボンニュートラルの観点から,木質バイオマス発電の普及に注目が集まっている.また,バイオマス発電の利用推進のために,重金属の吸着材として使用した後の籾殻を燃料としたバイオマス発電の普及も期待されている.今後,バイオマス発電のさらなる導入にともない,木質灰や籾殻灰が大量に排出されることが予想される.ところが,これらの灰類には重金属が含まれていることがあり,実際,多種多様な重金属の包含が確認されている.したがって,こうした灰類は最終処分場に廃棄されることになるが,最終処分場はひっ迫しており,2021年現在で,その残余寿命は年しかない.他方で,こうした灰類を無害化するには,現状での処理では多大なコストがかかる.カーボンニュートラルと廃棄物の減容を達成するには,重金属の溶出を防ぎつつ,灰類を大量に再資源化することが望まれる.その手法の有力な候補として,こうした灰類のコンクリートへの混和が考えられる.しかしながら,木質灰や籾殻灰を混和したコンクリートのワーカビリティーや圧縮強度等の性能は普通コンクリートより低くなる可能性があり,さらに,コンクリートの性能変化は,コンクリートの重金属封じ込め機能の低下につながる可能性がある.そこで本研究では,木質灰や重金属吸着籾殻灰を混和したコンクリートのフレッシュ性状,ならびに圧縮強度や乾燥収縮等の硬化後の性状について,普通コンクリートとの比較を行うことにより,木質灰や重金属吸着籾殻灰を混和したコンクリートの利用可否を検討した.さらに,これらの灰類の混和によってコンクリートの性能が変化した際における重金属溶出量増減の有無を確認した.その結果,灰類を混和したコンクリートは混和剤添加量を調整することで,品質的に問題のないスランプと空気量を有すること,わが国における標準供用期間の耐久設計基準強度を超える圧縮強度を有すること,重金属溶出量は普通コンクリートと同程度であることが確認された.中には,普通コンクリートの性能を上回る事例もあった.これらより,灰類混和コンクリートについては,通常の使用が可能であり,とりわけ,灰類をセメントに置き換えることで,さらなるカーボンニュートラルへの貢献につながることが判明した. 日時 2023年2月20日 17:15-18:05 会場 ICEDSルーム(遠隔教育調査研究室)/香川大学幸町北2号館2F +zoomによる遠隔配信 ご参加は、こちらの申し込みフォームから
[2/24開催]GCS45 豊島のいま~水と自然・人の持続的関係性をデザインする
ワークショップ:趣旨と概要 急速に過疎化の進む豊島は、人と自然の持続的関係性をデザインする重要なフィールドである。香川大学もこの課題に早くから取り組んできた。今年度も持続可能な地域のデザインに向けた諸研究と、学生・大学院生の教育のフィールドとしてかかわりを強めた。悠久のようにみえる自然の営みも、自然と人との関係性の変化の中で、驚くほど急速な変化を見せている。こうした変化に対する、自然の側から、そして社会の側からの3つのアプローチを軸に、豊島における持続的な未来を展望しながら「豊島のいま」を確認する。 日時 2023年2月24日 16:20-18:20 会場 ICEDSルーム(遠隔教育調査研究室)/香川大学幸町北2号館2F +zoomによる遠隔配信 報告 趣旨説明:寺尾 徹(香川大学教育学部教授・ICEDS共同代表) 「井戸と生活知から考える豊島の水環境」 八塚 正剛(香川大学工学研究科大学院生(M2)) 「香川県下で広がる樹木病"ナラ枯れ"とは?/もし豊島で広がったら?」 小宅 由似(香川大学創造工学部助教) 「よそ者が豊島に関わる方法:観光とアートの視点から」 小坂 有資(香川大学大学教育基盤センター特命講師) コメンテーター:石井 亨(NPO「てしまびと」代表) ご参加は、こちらの申し込みフォームから
[2/21開催]GCS43 快適性・省エネルギー・コロナ対策をどうバランスするか?
セミナー 講演:山本高広(香川大学創造工学部助教) 趣旨と概要 建築物の低炭素、省エネルギーを進める具体的な方法としては、一般的には各種設備や断熱性能といったハードウェア面の改善や、空調設定温度28度に代表される一律の設定変更を連想される方が多いと思います。もちろんこれらは有効な手段であり、定量的に効果を見込める堅実な方法と言えます。一方で、このような1㎡あたりの省エネルギー追求とは別に、機器や室の利用実態や、CO2に代表される空気質の動向を注意深く分析すると、個々人の快適性や安全性を損なわない別の省エネルギーの可能性が見えてきます。本発表では、香川大学内で実施した過去のエネルギー消費調査や、CO2実測調査のデータを用いつつ、快適性、省エネルギー、コロナ対策を無理なくバランスする方法について、話題を提供したいと思います。 日時 2023年2月21日 16:20-17:50 会場 ICEDSルーム(遠隔教育調査研究室)/香川大学幸町北2号館2F +zoomによる遠隔配信 コメント: 植田和也(香川大学教育学部附属高松小学校長) 「附属高松小学校のSDGs教育~省エネプロジェクトとのコラボにも触れて ご参加は、こちらの申し込みフォームから!